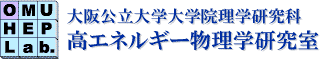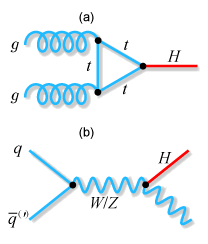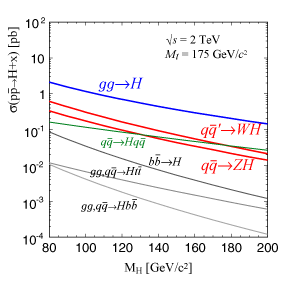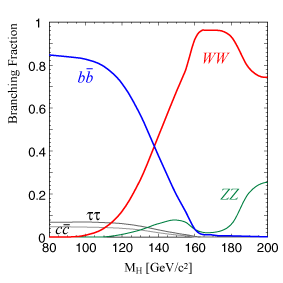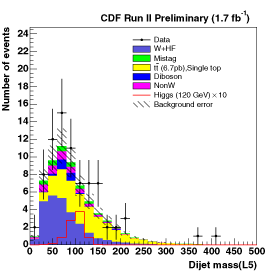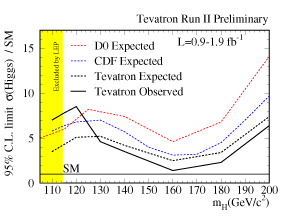ヒッグス粒子の探索
「物質の質量はどうやって生まれたのでしょうか?」 この素朴な疑問には昔から多くの人々が思いを巡らせてきました. 実際のところ,物質の“質量”は色々な階層スケールにおいて順次獲得されてきているのですが,それでは,物質の最小単位である“素粒子”の質量は何処から 来ているのか? この問いに物理学は答えを出そうとしています.長年にわたる素粒子物理学の研究から,質量の獲得には“真空”の性質が大きく関わっているということが分 かってきました. 1964年にイギリスの P. W. ヒッグスは,自発的対称性の破れによって真空に相転移が起こることで素粒子が質量を獲得したという理論を提唱しました.このメカニズムをヒッグス機構と呼びます. 真空にはその名の通り何も無いと思われるかもしれませんが,素粒子の世界にまで掘り下げると,そうではありません.ヒッグス機構によれば,現在の真空には 有限値の真空期待値を持つ“ヒッグス場”と呼ばれる場が満ちていて,常に素粒子と相互作用を繰り返していると考えられています.この相互作用を起こす粒子を“ヒッグス粒子”と呼び,H または h の記号で表します.初期宇宙ではもともと素粒子は光速で自由空間を運動していたのですが,真空の相転移により生じたヒッグス粒子が次々と素粒子に絡みつき,もはや素粒子は光速で運動できなくなった結果,素粒子は質量を獲得したというシナリオです.(図1)
この考えを検証するためには,ヒッグス粒子を実際に検出することが必要です.これまでも大型加速器が作られる度に検出が試みられてきましたが,未だ発見されていません.1989年から稼動を始めた CERN の大型電子・陽電子衝突型加速器 LEP による探索実験によって,ヒッグス粒子が存在するためには,その質量 MH が 114.4 GeV/c² よりも重くなければならないということが分かりました.しかし,LEP は来年稼動開始予定の大型陽子衝突型加速器 LHC 建設のために2000年に運転を終了してしまいました.2007年現在,ヒッグス粒子を探索できるのは世界中で Fermilab の Tevatron だけです.
Tevatron は重心系エネルギーが 1.96 TeV の陽子・反陽子衝突型加速器です.ヒッグス粒子が生成される素過程は,クォークと反クォークの衝突からベクトルボゾンの中間状態を経てヒッグス粒子が放出される“ベクトルボゾン随伴生成”(図2(a))
qq′ → WH, qq → ZH
および,グルーオンどうしが衝突してヒッグス粒子になる“グルーオン融合生成”(図2(b))
gg → H
が主な生成過程で,その断面積は理論計算によると図3に示すように 0.1 ∼ 1 pb です.Tevatron の現在のルミノシティは約35 pb−1/週なので,ヒッグス粒子は1週間あたり約40個生成されているという計算になります. しかし,それ自身不安定なヒッグス粒子は,生成した後すぐに崩壊を繰り返し,我々は最終的に安定な粒子群になった状態しか観測することは出来ません.崩壊様式は図4に示すように, MH < 130 GeV/c² では bb, MH > 130 GeV/c² では WW が主な崩壊モードになります.b クォークはさらに軽いクォークへ崩壊し,W ボゾンもレプトン対や軽いクォーク対へと崩壊します.ヒッグス粒子を観測するためには,運動学変数の分布特性などを利用して,大量のバックグラウンド事象の中から ヒッグス粒子の崩壊事象を選別する必要があり,この過程で観測効率は0.1%の レベルになってしまいます.従って,毎週40個のヒッグス粒子が作られていても,それらを実際に観測するには数年分のデータが必要になります.
TevatronでのCDF実験(大阪市立大学が参加)とDØ実験では,2001年以来の継続的なデータ収集の結果,現在までに約2.5 fb−1 のデータが蓄積されました. 今回はそのうち 1 ∼ 2 fb−1 の陽子・反陽子衝突事象のデータ解析が終了し,ヒッグス粒子の探索結果が公表されました. 生成と崩壊に関して
qq′ → WH → ℓνbb
qq → ZH → ℓ+ℓ−bb / ννbb
gg → H → WW → ℓ+ℓ−νν
の各モードを解析し,図5はその中の qq′→ WH → ℓνbb の結果です.この図は bb 候補の不変質量分布を表していて,もしヒッグス粒子が十分な統計で存在すれば,図中の赤線のようなピークが出来ます.今回の解析ではその他のモードを含め て,ヒッグス粒子の生成を証拠付ける信号は得られませんでしたが,この事実より,図6に示すようにヒッグス粒子生成断面積の上限値が計算されます.図は理論計算が与えた予想値との比を表しています.これを見ると,現在のところはまだ理論予想値(縦軸が1のSMと書かれたライン)にまで感度が達していませんが, ヒッグス質量によっては2倍を切っているところもあります.今後,Tevatronではますますデータ収集とデータ解析が進められていくので, 感度が十分に上がったところでは,近い将来にヒッグス粒子が発見されるかもしれません.